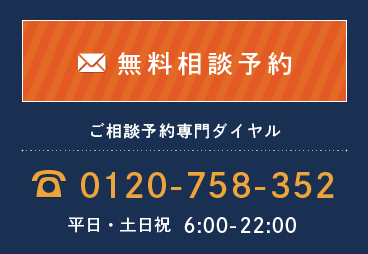
※平成30年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者の令和元年10 月31日までの申告又は処理(更正、決定等)による実績を、全数調査の方法で調査・集計したものです。
被相続人数での人数
| 申告した人数 | 課税された人数 |
|---|---|
| 12,388人 | 9,842人 |
■課税状況での課税価格
愛知県の合計で1兆3,825億円で、被相続人1人当たりでは1億4,047万円
■納付税額
愛知県合計で1,727億円で、課税状況での被相続人1人当たりの納付税額は1,755万円
相続税法の改正により、申告者は増加しています。
しかし課税対象の拡大により中間層への課税が進み、課税被相続人1人あたりの納付税額は減少しています。
一方、愛知県の平成30年の死亡者総数は68,833人です。
愛知県の平成30年の 相続税申告数(被相続人数)/死亡者総数 は、17.98%
課税状況での 被相続人数/死亡者総数 は、14.28%です。
死亡者数には、乳幼児や未成年者も含まれているので 高年齢者(55歳以上)に限れば、相続税申告割合(被相続人数)は、20%近くに、課税納付となる被相続人数では、16%前後になると思われます。
平成25年度税制改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)により、相続税の基礎控除が縮小され、税率が引き上げられました。
この相続税の基礎控除の縮小により、課税範囲が約2倍に広がり、申告義務者の割合は、名古屋市、豊田市、一宮市、岡崎市など住宅地価格が高い住宅地を抱える名古屋市の区や主要都市では、愛知県の平均値より高くなると推測されます。
平成30年中に亡くなられた方(被相続人数)は約136万人(平成29年は約134万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万6千人(平成29年は約11万1千人)で、課税割合は8.5%(平成29年は8.3%)となっており、平成29年より0.2ポイント増加しました。
国税庁の平成30年度 相続税の統計では、
申告状況
被相続人数:1,362,470人, 課税状況:116,341人ですので、申告状況から、平成30年の相続税申告数(被相続人数)/死亡者総数 は、8.5%となることがわかります。
(1)被相続人数に対する相続税申告割合
| 全国 | 愛知県 |
|---|---|
| 8.53% | 17.98% |
(2)1人あたりの相続税課税価格
| 全国 | 愛知県 |
|---|---|
| 1億3,956万円 | 1億4,047万円 |
(3)1人あたりの相続税納付税額
| 全国 | 愛知県 |
|---|---|
| 1,813万円 | 1,755万円 |
愛知県では、相続税の申告割合、課税割合とも、全国平均より50%以上割合が高いです。
課税価格では、全国平均よりやや高く、納付相続税額は全国平均よりやや低いです。
これは、愛知県は全国に比べて、中間層の割合が高く、課税者数が多く、かつ1件当たりの納税額も高いということです。
| 順位 | 都道府県 | 平均貯金額(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 2,503 |
| 2 | 神奈川県 | 2,328 |
| 3 | 東京都 | 2,295 |
| 4 | 埼玉県 | 2,263 |
| 5 | 兵庫県 | 2,261 |
| 6 | 千葉県 | 2,234 |
| 7 | 愛知県 | 2,152 |
| 8 | 栃木県 | 2,135 |
| 9 | 岡山県 | 2,112 |
| 10 | 広島県 | 2,083 |
引用元:都道府県別の平均貯金額ランキング1位が
意外な県でビックリ!(株JIN.com)
一方、固定資産(土地、建物など)の保有については
都道府県別 一人あたりの固定資産税負担額(個人分)は、愛知県は40.2千円で、東京都の45.5千円に次いで、2位です。
これは、 一人あたりの不動産などの固定資産保有額が高いことを示しています。
参照:地方税における資産課税のあり方に 関する調査研究 88ページ
このように、愛知県は、一人当たり不動産の保有額が高く、かつ、貯蓄額が高いということです。
したがって、相続税の課税対象の拡大(基礎控除の縮小)により、愛知県では、かなり広範囲で相続税申告および課税対象者が多くなりました。
全国でも、県民一人当たりの資産保有額が高い地域であります。
ですので、愛知県には突然相続問題が発生して頭を悩ませる方も多く、当事務所にもそのような方がたくさんお見えになられます。そんなことのないように是非、早めに対処することが肝心です。もし、相続や生前対策でお悩みなら、名古屋総合法律事務所までご相談ください。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
上述の年齢を含む一定の要件に該当し、これを選択する届け出を事前に行えば、贈与財産の額から基礎控除額および複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額にしか課税はされません。
ここでいう基礎控除額は年110万円で、特別控除額は総額で2500万円です。これを贈与財産の額が超えた場合に一律20%の税率で贈与税が課されます。
この制度を選択した親族間においては、毎年贈与額から110万円をまず控除し、特別控除額の残額(2500万円から前年までに控除した分を差し引いた額)を控除し、その年の申告納税の要否を判断することになります。
重要なことは、この制度を選択しても課税自体が免れる訳ではなく、いわば相続時まで課税が先送りされるかたちになっているということです。
すなわち、相続時に納税を「精算」する制度ですので、贈与者である父母や祖父母が亡くなり相続が開始された際の相続税計算の中に、この相続時精算課税制度を適用した財産が全額加算され、結果として相続税は負担することになります。
上述の特別控除額を超えて、20%の税率で納付した贈与税額は、この相続税計算の中で控除され、もし相続税額をこの控除額が上回った場合は還付されます。受贈者(相続人)は相続税率に基づく税金を最終的に負担することになります。
この相続時精算課税制度が直接的に有効な生前対策とはならず、単なる課税の先送りにしかならないケースも多くありますが、相続財産に加算することになる贈与財産の価額が贈与時の価額とされているため、下のような場合は有効に作用すると言えます。
ただ、この相続時精算課税制度を選択したことによるデメリットもあり、
などが挙げられます。
これまでは、この中の暦年課税に戻れない(両制度を併用できない)というデメリットの影響が大きく、相続時精算課税制度は利用し難いという問題がございましたが、令和5年度税制改正により、先に述べた年110万円の基礎控除額が新設され、このデメリットはかなり解消されました。
令和6年以降に相続時精算課税制度に基づく贈与を年110万円の基礎控除額の範囲内で行った場合は、その年の贈与税が課されない上に、将来の相続開始に伴う相続税計算に加算する必要がありません(2500万円の特別控除額とこの点で異なります)。
加えて、この基礎控除額の範囲内での贈与額は、相続開始前の一定期間(相続開始時期により3年から7年の間に定まります)に行われた贈与の額を相続財産に戻し入れなければならないという、いわゆる「生前贈与加算」の対象にもなりません。
そのため、将来相続人となる子への贈与につき、年110万円以内で行うと決めている親子間などについては、子があえて相続時精算課税制度を選択し適用した方が、この生前贈与加算がない分だけ有利と言える状況になっています。
これまである程度限定されたケースでしか利用されていなかった相続時精算課税制度ですが、令和6年以降の贈与では子への有効な生前対策として活用されることが見込まれています。
なお、相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を、一定の書類(受贈者の戸籍抄本等)を添付した上で、受贈者の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
ただし、110万円の基礎控除額の範囲内に年間の贈与額が収まる場合は、贈与税申告書を提出する必要はありません。選択する最初の年に「相続時精算課税選択届出書」のみを提出すれば足ります。
近年の税制改正により、この相続時精算課税制度は生前対策としての存在意義が増しました。改正後の制度内容や要件をご確認いただき、有用にご活用いただければと思います。
愛知県春日井市の管轄税務署は、小牧税務署です。
小牧税務署の管轄区域は、春日井市 犬山市 江南市 小牧市 岩倉市 丹羽郡(扶桑町、大口町)です。
平成30年中に開始した相続で令和元年10月31日までの申告税納付数
| 課税された相続人の数 | 課税金額(億円) | 納付した相続人の数 | 納付金額(億円) | 被相続人の数 |
|---|---|---|---|---|
| 2,312人 | 1,071億円 | 1,953人 | 98億円 | 900人 |
・平成30年の小牧税務署の管轄区域
死亡者数に対する相続税申告割合(被相続人数)は19.13%、相続税納税割合は14.80%です。死亡者数には、乳幼児や未成年者も含まれています。高年齢者(55歳以上)に限れば、相続税申告割合(被相続人数)は、21%近くになると思われます。
・鉄道について
春日井市は、名古屋市に隣接しており、市の真ん中を東海旅客鉄道 (JR東海)の 中央本線が(名古屋市守山区)- 勝川駅 – 春日井駅 – 神領駅 – 高蔵寺駅 – 定光寺駅 -(岐阜県多治見市)へと通っており 名古屋鉄道 (名鉄)の小牧線が(名古屋市北区)- 味美駅 – 春日井駅 – 牛山駅 – 間内駅 -(小牧市)へと、 東部では、愛知環状鉄道(愛環)が高蔵寺駅起点に 、瀬戸市、豊田市、岡崎市JR岡崎駅へと通っています。
・高速道路について
高速自動車道は、東名高速道路(名古屋市守山区)- (22)春日井IC -(小牧市)、中央自動車道(小牧市)- 内津峠PA -(多治見市)、名古屋第二環状自動車道(名古屋市守山区)- (10)松河戸IC – (11)勝川IC -(名古屋市北区)と通っております。
このように、春日井市は、名古屋市に隣接し、かつ鉄道・高速道路網が発達しており、名古屋市のベッドタウンとしても開発が進んでおります。 そのため、愛知県春日井市は、住宅地価格が上昇傾向にあります。
すると、今後、春日井市では、一層、相続税申告割合は高くなり、納付相続税総額は増額となります。中間層への課税範囲が次第に拡大していき、相続人1人当たりの納付税額は減少していくと推測されます。
したがって、中間層での相続税対策が必要になるとともに、相続税額が多額なると推測される資産家の方は、第2次相続での相続税対策を含めて、本格的に相続税専門税理士事務所に相続税対策の実行をご依頼されることが肝要と思います。
春日井市は、名古屋市に隣接しており、中央本線、名古屋鉄道 (名鉄)の小牧線、愛知環状鉄道(愛環)と3つの公共交通機関が通っています。
名古屋市のベッドタウンとして機能しており、開発が進んでいるため、愛知県春日井市は、住宅地価格が上昇傾向にあります。
| 世帯数 | 137,340 |
|---|---|
| 人口総数 | 311,338 |
| 男性 | 154,871 |
| 女性 | 156,467 |
| 出生数 | 2,688 |
|---|---|
| 死亡数 | 2,599 |
| 自然増減数 | 89 |
| 春日井市平均 | 335万円 |
|---|---|
| 愛知平均 | 321万円 |
| 全国平均 | 276万円 |
| 愛知県春日井市 | 11万872円/m²、36万6,521円/坪 | +2.09% |
|---|
| 住所 | 最寄駅 | 距離 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 松新町1丁目4番 | 勝川 | 0m | 91.6万円 /坪 | +5.73% |
| 八光町1-20-1 | 勝川 | 380m | 62.8万円 /坪 | +5.56% |
| 瑞穂通6-7-1 | 春日井 | 1500m | 58.2万円 /坪 | +2.33% |
| 松新町4-3-12 | 勝川 | 350m | 55.2万円 /坪 | +4.38% |
| 松新町2-38 | 勝川 | 550m | 51.2万円 /坪 | +3.33% |
| 六軒屋町字東丘17-163 | 春日井 | 2000m | 49.9万円 /坪 | +0.67% |
| 八幡町45-12 | 勝川 | 1200m | 46.9万円 /坪 | +2.90% |
| 春見町58-2 | 春日井 | 1600m | 45.6万円 /坪 | +2.99% |
| 鳥居松町6-49-2 | 春日井 | 1300m | 45.0万円 /坪 | +1.49% |
| 妙慶町3-64-3 | 勝川 | 1600m | 44.3万円 /坪 | +3.08% |
引用元:愛知県春日井市の土地価格(地価公示価格、路線価)
(地価公示価格チェッカー)
愛知県の最新・地価公示価格(地価公示価格チェッカー)
正味遺産額(※1)-基礎控除額(※2)=課税遺産総額
この課税遺産総額を基に相続税を計算します(ここでは税額計算の詳細は省きます)。
(※1)被相続人(亡くなられた方)の財産総額から、墓地や仏壇等の非課税財産を差し引き、さらに被相続人にかかる借入金等の債務、相続人が負担した葬式費用を差し引いた金額です。
(※2)ここまでは相続税がかかりませんよ、という非課税限度額のことです。法定相続人の数によって決まります。
つまり、相続税の節税対策は、この「課税遺産額」をいかに減らすか、ということです。
それには、正味遺産額を減らす対策と、基礎控除額を増やすという対策が考えられます。
1. 生前贈与を活用した相続税対策
2. 生命保険を活用した相続税対策
3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策

生前贈与を活用した対策としては、次のようなものが考えられます。
「500万円✕法定相続人の数」までの保険金には相続税がかかりません。この非課税枠を満たすような生命保険に加入する節税対策です。一般的には「一時払い終身保険」という保険商品に加入します。
最近では、相続税対策として80歳以上でも加入できる保険商品もありますから、検討してみると良いと思います。
<生命保険を活用するメリット>
墓地や墓石、仏壇等の非課税財産を生前に購入しておくというのも節税対策になります。
また、非課税財産ではないですが、家のリフォームを生前に行うというのも良いと思います。
それにより家の相続税評価額が増加しますが、一定の評価方法により計算されますので、現預金のままで加算されるよりは小さくなります。
そのほかに、高価な宝飾品や子や孫のために車等を購入する(所有者と使用者は異なってもよい)のも一つの方法です。
これには養子縁組を活用した相続税対策があります。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので、相続人が増えると基礎控除額が増えます。それにより課税遺産総額が小さくなります。
また、相続人が増えると、税額計算において相続税率(累進課税)が低く抑えられるため、相続税の総額が少なくなります。
相続税の総額は、課税遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得したものとして求めた相続税の金額を合計して計算するためです。
※ただし、法定相続人に含めることができる養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
先週12月14日、自民党および公明党より、平成31年度税制改正大綱が公表されました。この先、12月下旬に閣議決定され、来年1月には国会に改正法案が提出される流れとなります。
ここ2年、配偶者控除の大幅な見直しや給与所得控除から基礎控除へのシフトなど、個人所得税関連での改正が目立っておりましたが、今年度の大綱では、来年10月の消費税率引上げに伴う景気への影響を考慮した諸々の緩和措置が前面に出されています。
具体的には、住宅ローン控除の適用期間を10年から13年に延長する措置、自動車税の恒久的引下げなどが盛り込まれております。
ここでは、今回の大綱で決定された相続税・贈与税関連の主な改正事項を速報でお知らせしたいと思います(詳細につきましては改正法案が出される頃に本ブログでご紹介します)。
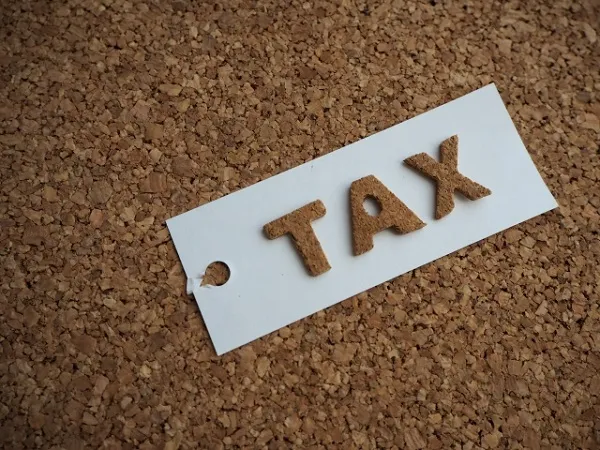
今回の改正において、「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」として、法人の事業承継制度と同様の相続税および贈与税の納税制度を個人事業においても利用できるよう、新制度が創設されることになります。
現時点では10年の時限措置とされており、法人の場合と同様に承継計画を作成し確認を受けることが要件とされます。
対象となる資産は、青色決算書に計上されている土地、建物およびその他の減価償却資産で、土地は400㎡までといった上限が各々設定される見込みです。
なお、既存の事業用宅地に対する小規模宅地等の特例制度とは選択適用となることが示されています。
平成31年3月限りとされていた教育資金の一括贈与非課税措置および結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の適用期限が2年延長されます。
その一方で、贈与資金を信託等に供する年の前年における受贈者(子や孫)の所得金額が1,000万円を超えている場合には、当該信託等により取得した信託受益権等には本措置が適用されないという適用制限が設けられることになります。
また、教育資金の範囲から、学校以外に支払われる金銭のうち、受贈者が23歳に達した以降に支払われる一定の金銭が除外される模様です。
成人年齢が18歳に引き下げられる民法改正に合わせて、制度適用のための年齢要件が20歳以上ないし未満とされていた規定が「18歳」に変更されます。
具体的には、
ところで、改正民法で創設される「配偶者居住権」の相続税における評価額の計算方法についても、本改正において明らかにされます。
相続税の改正事項ではないのですが、相続に関連する改正として、3年前の税制改正で新設されたいわゆる「空き家特例」に関して、その適用期限が4年延長される上、その適用要件の一部が緩和されることとなります。
具体的には、老人ホーム等に入居することにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋等についても、一定の要件を満たせば、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本制度の適用が認められる見込みです。

幼児のように民法上の意思能力がないとされる者が行う法律行為は無効とされるため、相続税申告書の作成や提出、税金の納付などは親権者である親が全て代理して行う必要があります。申告書への署名押印も親権者が代わって行うことになります。
(概ね中学生以上の一般に意思能力を有していると解されている未成年者についても、法律行為を行うには親権者の同意が必要とされるという制約がありますが、申告書の作成提出のような単に自己の負担すべき納税額を確定させるための行為は単独で行うことができると解されており、自身で署名押印しても差し支えないものとされています。)
相続税申告書の作成や提出を税理士に委任することももちろんできますが、契約は親権者が代理して(概ね中学生以上の場合は親権者の同意に基づいて)行う必要があります。
未成年者が相続人となる場合にお気を付けいただきたいことは遺産分割協議を行う場合です。この場合、未成年者とその親権者である親は利益相反の関係に立つため、親が子の代理行為をすることはできません。そのため、親権者等が子のために家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てを行う必要があります。この手続きに基づいて選任された代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
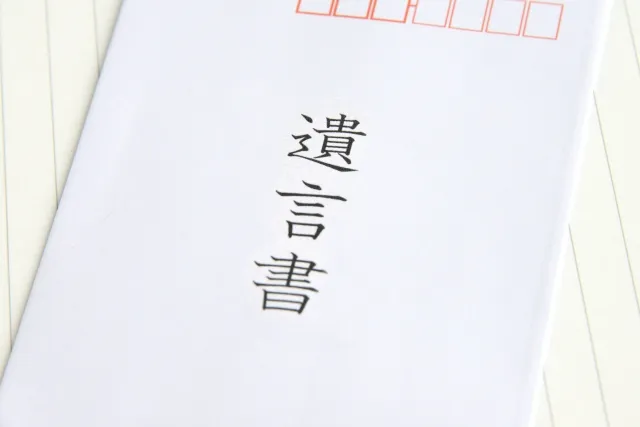
民法上の法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹)がいない方が亡くなり、その方の遺言や死因贈与契約が存在しない場合、利害関係者や検察官の申請により家庭裁判所が相続財産管理人の選任を行います。
この相続財産管理人が相続人捜索や債権者確認のための公告や特別縁故者への分与等の一定の手続きを行い、最終的に残った相続財産があれば全て国庫帰属となります。
このようなケースにおいては、相続ないし遺贈により財産を取得する者がおりませんので、相続税の申告納付義務は誰にも生じないことになります。
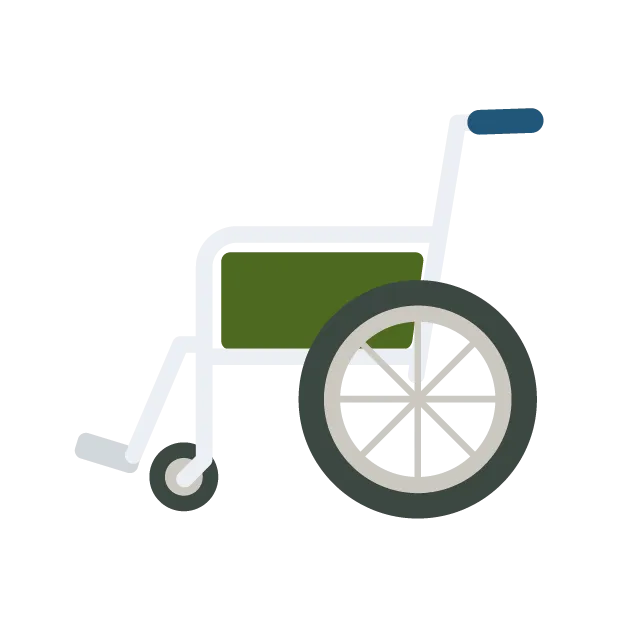
所得税と同様に相続税にも障害者控除の制度はあり、相続や遺贈により財産を取得した方が障害者である場合、一定の税額控除を受けることができます。
障害者控除を受けられる方は次の要件の全てを満たす方です。
ここでいう「法の定める障害者」は、一般障害者と特別障害者に区分され、次の表に示す者が該当します。
| 一般障害者 | 特別障害者 | |
|---|---|---|
| 指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち、 | 重度の知的障害者とされた者以外の者 | 重度の知的障害者とされた者 |
| 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が、 | 2級または3級である者 | 1級である者 |
| 身体障害者手帳の障害の程度が、 | 3級から6級である者 | 1級または2級である者 |
| 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法での障害の程度が、 | 4項症から6項症の記載のある者他 | 特別項症から3項症の記載のある者 |
障害者控除の控除額は、対象となる方の年齢が85歳に達するまでの年数に、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円をそれぞれ乗じて計算します。
これを計算式で示すと次のようになります。
(85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円または20万円
相続税の障害者控除は大変特徴的な面があり、障害者控除の金額が障害者本人の相続税額を超える場合(本人が控除しきれない金額がある場合)には、 この超過分を同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者のうち、障害者の扶養義務者に該当する者の相続税額から控除することができます。 ここでいう扶養義務者とは、
なお、障害者控除は相続税法上の特例ではありませんので、配偶者の税額軽減制度のように申告書を提出して控除額計算を示す必要はありません。 すなわち、障害者控除を加味した結果、納税額が発生しないことが分かった場合、申告書を提出する必要はありませんので、ご留意ください。

相続税の申告は、その申告書の様式を見ても相続人全員が共同して署名押印して提出することが義務付けられているように思えますが、法律上はあくまで相続人各人がそれぞれ納税義務者であり、個々に申告することがむしろ原則とされています。
相続税法上、「申告書の提出先の税務署長が同一であるときは共同して提出することができる」と規定されている(27条5項)一方で、その附則において、「当分の間」としながらも、「申告すべき相続税に係る納税地は...被相続人の死亡の時における住所地とする」と定めているため(附則3項)、実務上は相続人が一緒に一つの申告書を連名で、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出することが通常となっています。
とは言っても、相続人が各々で申告書を作成すると、手間やコストが余計にかかる上、申告書に記載される遺産の内容やその評価額に違いがあると、受け取った税務署側はその検証と調整を行う必要が生じ、税務調査が実施されることにつながります。
税務調査について詳しくはこちらをご覧ください。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と比較的期間が長いので、遺産分割がまとまらないケースなどは仕方ないにしても、相続人が離れて暮らしていることだけが理由でしたら、相続人のお一人が取りまとめ役になり作成する、あるいは税理士に依頼するなど、共同で提出できるよう事前に相続人間でお話しされることをお勧めします。

相続財産のほとんどが不動産である場合などは、相続税は発生するもののそれを納付する金銭が不足するという状況が生じます。相続税の納付手続きにおいてはこれを救済する手段として、年 賦での納付を認める「延納」の制度を用意し、それでも納付できない場合のために「物納」の制度を設けています。
このとおり、相続税の物納は希望すればできるというものではなく、あくまで延納によってもなお金銭での納付を困難とする事由がある場合にその納付できない金額の分だけ適用できるという制度です。
物納の対象となる物は、相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産で日本国内にあるものですが、適用にあたり優先順位があり、原則として、
①不動産、上場株式、国債等
②非上場株式等
③その他動産
の順に従い物納に充てられます。
ただし、抵当権などの担保の付いている不動産や、譲渡制限のある株式などは、管理処分不適格財産として物納の対象から除かれますのでご注意ください。

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会